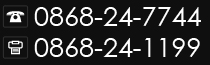音楽監督メッセージ④
音楽祭始まる


いよいよ音楽祭の開幕である。私は東京での仕事をほうり出し、私にとっての〈ふるさと〉のような街津山に、今回はできる限り滞在することにした。30年前とは街の様子もかなり変化し、なじみの食べもの屋も飲み屋も姿を消していたりするが、まったく変化しないのが、鶴山城の高く聳え立つ城壁である。来年から2年間の改築工事に入るという津山文化センターの前の喫煙所のイスにすわって煙草をくゆらせ、高高と組みあげられた石垣のそりのある形状を眺めていると、森忠政が17世紀はじめに築城に着手して長い年月をかけて完成した歴史が手にとるように理解される。津山市はまさに長く豊かな歴史と文化の街であり、江戸時代に入ると津山藩の藩医であった宇田川榕菴に代表されるような蘭学(オランダ学)の栄えた街になった。
蘭学をイメージの中心においたコンサートを洋学資料館で開きたいと思いたち、資料館の大倉淳一館長、田中美穂学芸員、音楽祭事務局員の松田杏子の諸氏とともに何度も相談会を持った。こうしてオランダのアムステルダム音楽院教授のヴァルター・ファンハウヴェやその弟子の田中せい子らによるリコーダーのリサイタルを資料館の小さなホール(GENPOホール)で開催することになった。そのコンサートのチケットはすぐに完売になり、当日は熱心な聴衆の方々が早くから会場につめかけた。ファンハウヴェは、今日のリコーダー界のトップランナーであり、ブリュッヘンと肩を並べる名手である。リコーダーと言うと小中学校時代の縦笛を思い出す人が多いかもしれないが、古楽器としてのリコーダーは、背丈ほどの長い笛から小さなものまで各種さまざまであり、それらの楽器を使ったファンハウヴェのソロや3人のリコーダー奏者のアンサンブルからは、単純な笛から出てくる単純な旋律というのではなく、大げさに言えば、オーケストラにも匹敵するような多様で多彩な響きの海が作り出される。私たちの時代に音楽史を学んだ者は、ネーデルランド楽派とか、フランコ・フランドル楽派の音楽として学んだものである。
洋学資料館は、このコンサートの会場を提供してくれただけではなく、音楽祭との協力のもとに学芸員の田中美穂氏が中心になり、「絵画史料に見る江戸の洋楽事始」という充実した展示会を、資料館の所持している資料とともに、神戸市立博物館その他から資料を借用して開催し、そして、全48ページからなるアカデミックな図録を作成された。図録の表紙には、宇田川榕菴の描いたオランダ軍の兵士がトロンボーンを吹く姿が紹介されている(「和蘭王国軍装図譜」)。宇田川榕菴の画筆はすぐれたものであるが、しかし彼は絵画以上に音楽に強い興味を持っていたことはひろく知られている。シーボルトとも親しかった彼の『大西楽律考』は、楽器や楽譜などの洋楽学習ノートであり、西洋音楽に関する日本最初の音楽理論書であると言っていいだろう。
音楽に長じていた榕菴をテーマにするなら、さまざまな音楽会が考えられるが、私が以前からあたためているテーマは、榕菴も深く研究していた長崎の出島で上演された喜歌劇(opérette)と呼ぶよりは小唄入り喜劇(comédie mêlée d’ariettes)の復活上演である。作品名は《2人の漁師とミルク売り娘》。古楽器の演奏家、演劇の演出家、声楽家、音楽学者などが、時間をかけた準備をすれば、きわめて画期的な上演になり、たんに津山市だけではなく、東京その他での上演も可能になるだろう。東京の流行を津山で模倣する時代はもう過ぎつつあり、今や地方から中央に新しい視点からの文化を発信する時代である。もし11回目の音楽祭が開かれるとすれば、遺言としてこのプロジェクトの提言を書き記しておきたい。
さて、今回の主要テーマ「G. マーラーと同時代の音楽」に沿って、10月21日にはR. シュトラウスの《交響詩「死と変容」》とG. マーラーの《交響曲第4番》が演奏された。《交響詩「死と変容」》は、下野竜也が好んでとりあげる作品で、かつて勤務していた上野学園大学のオーケストラでもとりあげており、下野は作品のすみずみまで知り尽くし、R. シュトラウス独自の色彩豊かなオーケストラのパレットを引き出していた。マーラーの《交響曲第4番》は、例によって、明るい鈴の連打のような音型にはじまり、その音型は最終楽章まで続いてゆく。第4楽章の〈Sehr behaglich(とてもくつろいで)〉においては、私たちは、平安な心のなかで明るい天国に遊ぶことができた。
「マーラーと同時代の音楽」というテーマから日本の音楽を考えると、日本小学唱歌の時代であり、《ふるさと》(高野辰之作詞、岡野貞一作曲)を番場俊之氏の編曲でとりあげた。下野指揮・京響・番場によるオーケストラ編曲というたいへんぜいたくな装置で、《ふるさと》を全員で歌うことができた。京都に生まれ、アメリカに留学した番場氏は、現在ベルリンに定住している。今回はこの演奏に立ちあうためだけに帰国した。みなさんはどのような感想を持たれたか知りたいところである。「《ふるさと》を歌いながら私の両目から涙が流れました!」というのが、この音楽祭の会長代行である松田欣也氏(津山商工会議所会頭)の述懐の言葉である。
今回のフェスティヴァルでは、ロダン作のマーラーの胸像の除幕式が行われた。この胸像の由来について説明すれば、津山国際総合音楽祭の初期に2度来日したアンリ・ルイ・ド・ラ・グランジュが、パリのロダン美術館でマーラーの胸像を売りに出すから津山市で買わないかという話をもちかけてきた。その後、ロダン美術館、パリのグスタフ・マーラー図書館、津山文化振興財団のあいだで何度も交渉を重ねた結果、津山文化振興財団理事長の浮田佐平氏が会社で購入し、それを財団に寄付するということになった。浮田氏は第1回津山国際総合音楽祭のときから、マーラーの音楽の強力な推進者であり、今回もプログラム委員長という重職をつとめている。
音楽祭の10回の歴史のなかで、全員どなたでも参加できるパーティが開かれたのは今回が初めてだと思う。さまざまなアトラクションに彩られた記念宴会は、音楽祭の初日にふさわしい、とても楽しい催しであった。私が感激したのは、昔の友人たちに何人も出会えたことである。画家の飛鳥和子さん、田中勝子さん…。田中さんは、第6回目で私が音楽監督をつとめたとき、Festival Ladies Organization(FLO)の責任者で、さまざまなボランティア活動を統括してくださった人である。私は、音楽祭はボランティアの活動がない限り、長くは続かないと思うので、3年後にもしこの音楽祭が続くとすれば、ぜひ津山の女性にボランティア活動をお願いしたいと思う。
ともかく、10回目の音楽祭はどうやら無事に進行しつつある。もちろんこれには、現場のスタッフの日常的な努力が支えとなってのことである。現場監督の立場にある森元弘之さんと水嶋聖さん、スタッフの林晴美さん、松田杏子さん、足立温美さん、治郎丸巧さん、齊藤貴子さん、赤田憲待さん、西前敬さん、竹内治雄さん、漆坂由起さん。私は、これらの人々が高い事務能力とパソコンの技術を持っていることに敬意を表したいと思うが、それ以上に、事務局の受付に来る千客万来の市民の方々に対して、スタッフ全員が実に丁寧で細やかに対応していることに驚かざるを得ない。そう!音楽監督に対しても細やかで丁寧な対応をお願いしたいと存じます。また、10月29日に津山におうかがいします。